
ひどい話になってきました。
厚生労働省は10月11日、60歳から65歳へと段階的に引き上げている厚生年金の支給開始年齢について、2030年度を想定している引き上げ完了時期 を9年繰り上げて、今から10年後の21年度とする案を社会保障審議会年金部会に示しました。
また、支給開始年齢そのものを68~70歳へと遅らせる案も提示し、68歳とした場合の引き上げスケジュールを公表しました。
現在、厚生年金の支給開始年齢は60歳。男性は2013年度から3年おきに1歳ずつ引き上げ、2025年度に65歳となる計画です。女性は2018年度から上げ、2030年度に65歳となるはずでした。
これを「2年に1歳ずつ」の引き上げとし、計画完了を4年前倒しする案を軸に検討し始めたのです。
年齢受給年齢 引き上げ 気が遠くなるわ・・・

いきなり、こんな計画の前倒しなんかしたら、人生設計を堅実に考えている人ほど、老後の生活設計に直撃を受けてしまいます。一度決めたものを変えれば、制度への国民の信頼を失うのは当然のことです。
やっと年金受給できそうだなと思ったら、また支給年齢上がるかも知れないですし。気が遠くなります。
与謝野馨前経済財政担当相なんて1月21日に政府の新成長戦略実現会議で、「人生90年を前提にすると定年延長を考えないといけない。年金支給年齢の引き上げも考えなければいけない」って言ってましたからね。
前提にできるか!
こんな状況に絶望する人続出で、年金未納者は激増することでしょう。
貧困率過去最悪の16% 6人に1人は所得112万円未満 一人親世帯は半分以上貧困 子ども貧困率も最悪

もし20歳から年金保険料を納めるとすると50年も保険料を収めてやっと年金受給です。私でもあと20年以上。
そこから平均寿命まで10年しかありませんよ。50年払って10年しかもらえないということになります。
しかも、弁護士には定年がありませんが、普通のサラリーマンの定年が60歳だとしたら、定年まで働けても(そう上手く行くとは限りませんが)、定年退職後年金受給までの8~10年間は無職・無収入ということになるんですが、厚労省はその人達にどうやって生きろと言うんでしょうか。
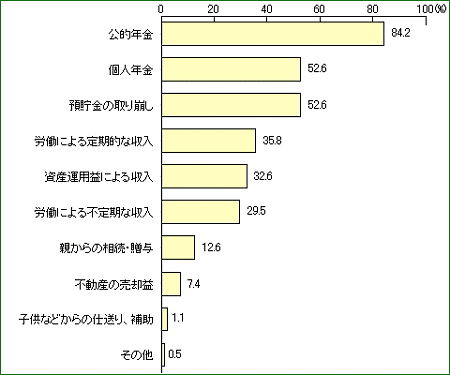
定年退職後の収入としてどのようなものを想定している/していたか
そもそも、年金問題って、保険料を支払っているのにそれが社会保険庁のミスで記録されていない人が何千万人もいたことがまず問題だったでしょう?
その訂正手続きもまだ全然終わっていません。

元祖年金問題と言えば、厚労省はかんぽの宿などグリーンピア事業のような不要不急事業を進め、国民が納めた保険料を年金の原資にしないで7兆円以上も流用していたわけです。
こういう無駄遣いもちっともメスが入っていません。
支払った年金は支払っていないことにされるかもしれないわ、何に使われるかわかったものではないわ、おまけにいつから支給され始めるかわからないわなんて、ひどすぎます。

下の図で明らかなように、日本は若年層と高齢層の貧困率が高いのです。日本の格差問題は世代間格差ではありません。
厚労省の案では現役世代が保険料ばかり納めてちっとも年金がもらえない話になっているのですが、財源問題を解決するならば、国民全員に負担を強いるべきではありません。
年金は社会福祉なんですから、高齢層であれば受給できるというのではなくて、高齢層でかつ低中所得であって初めて受給できるようにするべきです。
それが真の社会保障改革であり、格差の是正です。高資産・高所得の富裕層にまで年金を支給するほど、この国の財政に余裕はありません。
日本にも富裕税の導入を!年間所得100億円以上の富裕層は14%の税率でしか税金を支払っていない

安住財務相は来年にも消費税増税法案を国会に提出すると言っていますが、財源は低所得層からも一律に取る消費税を増税し、年金支給は富裕層にも支給するのでは、格差は拡大するばかりです。
財源は所得税・相続税・富裕税。年金支給開始は少なくとも65歳は動かさず、富裕層には支給しないというシンプルな改革を目指すべきだと考えます。
厚生労働省は全然反省していないと思われた方は
よろしかったら上下ともクリックしてくださると大変嬉しいです!
厚生労働省は11日、60歳から65歳へと段階的に引き上げている厚生年金の支給開始年齢について、2030年度を想定している引き上げ完了時期 を9年繰り上げて21年度とする案を社会保障審議会年金部会に示した。また、支給開始年齢そのものを68~70歳へと遅らせる案も提示し、68歳とした場 合の引き上げスケジュールを公表した。ただ、定年延長などの法整備は進んでおらず、早期実現は困難なのが現状だ。
60歳以上で働いている人の厚生年金をカットする「在職老齢年金制度」に関し、60~64歳の減額基準を緩める案も示した。賃金と年金の合計額が 月28万円を超えると年金を減らしているが、この基準を65歳以上と同じ「46万円超」へと緩和する案と、60~64歳の平均所得に合わせた「33万円 超」とする2案で、来年の通常国会への関連法案提出を目指す。
厚生年金の報酬比例部分の支給開始年齢は男性が13年度から、女性は18年度から3年に1歳ずつ引き上げられ、男性は25年度、女性は30年度以 降65歳となることが決まっている。しかし年金財政の悪化を踏まえ、厚労省は女性も男性同様13年度から引き上げを始め、ペースも「2年に1歳」へと速め ることで、男女とも21年度から65歳支給に完全移行する案を説明した。
さらに男女とも13年度からの引き上げとしたうえで(1)「3年に1歳」の引き上げペースは維持しつつ、支給開始を68歳に遅らせる(2)ペース を「2年に1歳」に速め、支給開始も68歳とする--計画表も示した。男女とも完全に68歳支給となるのは、(1)で34年度、(2)は27年度となる。 65歳支給の基礎年金も併せて68歳からの支給となり、1歳の引き上げで基礎年金給付費は年に約1兆円縮小する。
在職老齢年金制度の見直しは、「働くと年金が減るのでは高齢者の就労意欲をなくす」との批判に応えた。60~64歳の人は月額換算賃金と年金の合 計が月28万円を超すと、超過額の半分が毎月の年金から差し引かれる。年金と賃金が15万円ずつの人は月収30万円で基準を2万円超すため、超過額の半 分、1万円がカットされ、年金は月14万円となる。減額基準を「46万円超」に緩和した場合、給付総額は5000億円程度膨らむという。【鈴木直】
毎日新聞 2011年10月11日 20時59分(最終更新 10月12日 9時41分)
消費税法案提出に意欲 安住財務相「来年必ず」
安住淳財務相は12日、経団連会館で経団連の米倉弘昌会長と会談し、「来年には必ず消費税の法案を税と社会保障の一体改革とあわせて(通常国会 に)出す」と語り、平成24年度の税制改正で消費税率の引き上げを目指す考えを示した。安住財務相は「少子高齢化に直面する日本が今後も直接税に依存して いくのはもう無理」と表明。「消費税を国民の皆さんにお願いするしか道はない」と語った。米倉会長は「大いにやってほしい」と賛意を示し、双方は財政健全 化の重要性で一致した。
安住財務相はまた日本の環太平洋戦略的経済連携協定(TPP)参加問題について「メリットはなかなか目に見えない が、しっかりと説明し深く考えれば日本人は必ず結論を見いだしてくれると思う」と語り、参加に前向きな考えを表明。会談のなかで「将来を見据えて進んでい かなければならない。覚悟の問題だ」と強調した。
米倉会長は「震災復興や円高対策などを含む第三次補正予算を速やかに成立させていただきたい」と要望。会談終了後、記者団に対し「財務省と考えを同じくする点が多々あった。経済界もできるところは協力していきたい」と語った。
